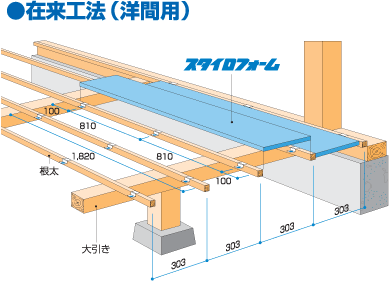CACICOブログ HOME > アーカイブ > 2017年5月のアーカイブ
2017年5月のアーカイブ
床断熱の代案は?
- 2017年5月24日 2:45 PM
- 「かしこい家」の性能
前回、床断熱には欠点があるよ。
と言う話をしました。
では、代案が必要ですよね。
それが基礎の断熱です。
基礎の断熱方法には、基礎内断熱と基礎外断熱の二つがあります。
この二つ、どちらが理にかなっているか。と言えば、圧倒的に基礎外断熱です。
ですが、現実にどちらがたくさん導入されているかと言えば、基礎内断熱なんですね。
理由は何と言っても「シロアリ」対策です。
いくら、防蟻断熱材を使おうが、保証を付けようが、
「でも、100%大丈夫とは言えないですよね」
と言う意見が必ず出てくるのです。
CACICOは、基礎内断熱でも床断熱でも、程度の差は有っても、シロアリ被害の対象だと思うのですが、
なぜか、基礎外断熱だけがやり玉に挙げられているのが現状です。
もちろん、防蟻対応を一切していない基礎外断熱は論外ですが、一度貼られたレッテルはなかなかに強固。
そんな風潮に一石を投じた(と勝手に考えている)のが、
今年の4月1日に開始したJOTOさんのしろあり保証1000です。
JOTOさん(城東テクノ)は、床断熱時に使う「基礎パッキン」という部材のトップメーカーなのですが、
実は基礎断熱用の部材も、多く手がけています。
しろあり保証1000は、シロアリの食害を受けたら、1000万円まで保証しますよ。
という太っ腹な保証なのですが、ポイントは、
床断熱でも、基礎内断熱でも、そして基礎外断熱でも対応する。
と言う所なのです。
それまで、
「基礎外断熱は、ちょっと危険な感じがする」
と思っていた人への説得力は、なかなかに大きい気がしているのです。
詳細は割愛しますが、JOTOさんの防蟻手法、それほどすごいものでは有りません。
でも、
「あのJOTOさんがOK出したのだから」
という側面がとっても大きい。
CACICOとしては、JOTOさんが基礎外断熱に貼られたレッテルを剥いでくれたと思っています。
・・・気が早いですかね。
足元の断熱を考える
- 2017年5月23日 11:55 PM
- CACICOの毎日 | 「かしこい家」の性能
住宅の断熱は、大きく3つに分かれます。
壁・床・天井です。
その中で、今回取り上げるのは「床」の断熱。
ダウ加工のホームページに分かりやすいイラストがありました。
写真で見るとこんな感じです。
この上に、床下地材と床材を貼っていくのですね。
見えているのは根太という材料で、この隙間を断熱材で埋める。
これは、壁の充填断熱とよく似ています。
壁は柱・間柱間に充填するのですから。
ですが、壁と床は、とても大きな違いがあります。
それは、壁を触ることはほとんど無いが、床は直接触るのが基本であるという事。
写真に見えている根太の下は、イラストで分かるように床下。
温熱環境的には外部です。
根太は一般的に303mmピッチなので、
普通に歩くと、必ず断熱材が無い所を踏むことになります。
話変わりますが、断熱の計算と言うのは、平均値なんですね。
壁で言えば、
「窓の面積×性能」と「断熱材の面積×性能」と「構造材の面積×性能」
を合計して、全体の面積で割る。
この考えだけで断熱を考えると、大きな落とし穴があります。
よくやるのはコストダウン目的で、小窓の性能を下げる事。
建物全体としては、ほとんど性能ダウンせず、コストはカットできる。
という理屈ですね。
で、その現実は、冬になると必ず結露を起こす窓が出来てしまうのです。
結露する窓がある一番の問題点は、建物内の湿度コントロールが非常に難しくなる事。
加湿しても、片っ端から窓で結露、つまり除湿してしまうからです。
温度と違って湿度の移動はとても早いので、その部屋だけでなく建物全体の湿度に影響を与えてしまうのです。
床断熱の話に戻ります。
計算上、断熱性能は担保されたとしても、足の一部は断熱材の無い所に接する・・・
もし室温が保たれていたとしても、床面に温度ムラがあったら、快適とは言えないでしょうね。
足が冷たいのが一番不快ですから。
その解決策として出てきたのが、基礎断熱と言う手法です。
次回に続きます。
ケトル交換
- 2017年5月13日 6:02 PM
- CACICOの毎日
おぉ、もの凄い期間ブログを休んでいました。
でも何も無かったように再開。
CACICOの朝は、コーヒーでスタート。
その時使うケトル・・・ヤカンを新調しました。
写真は、新旧揃い踏み、
手前側が、今まで使っていたものです。
見て分かるとおりメーカーは同じHARIO。
ガスレンジ用から、電気タイプに変更したのです。
この写真に理由が隠れています。
理由は油飛び。
料理する時、片付ける根性があれば良いのでしょうが、
面倒なため、油を被るハメに陥ってます。
選択肢は、
①普段はしまっておく
②電気タイプに変える
で、②を選択したのです。
気になったお湯が沸く迄の時間ですが、小コンロであればほぼ同じ。
実測したところ、25℃を90℃にするまで5分台でした。
購入したモデルは、温度設定が可能。
設定温度に達してからは、15分間の保温モードになる所も良いですね。
ちょっと目を離したために、お湯が沸騰し続けると言うのが防げます。
実際使ってみると、思った以上に快適です。
気になる点としては、
①本体にヒーターが入っているため、それなりに重い
②前回の設定温度を覚えるメモリー機能が無い
と言う所でしょうか。
①は、台座の方にヒーターを付けることが出来なかったのかなぁ?という素朴な疑問です。
で、②の方は、少し説明が要ります。
沸騰は加熱スイッチ一押しで出来ますが、
温度設定する場合は、温度設定+加熱スイッチを押します。
ここからが本題です。
温度設定幅は60℃~96℃なのですが、デフォルトが93℃。
これはメーカーが、コーヒー入れるなら93℃と考えているのでしょうね。
つまり、温度設定を行いたい場合は、93℃から変更していく事になります。
まぁボタンを何回か押すだけの話ではあるのですが、
メモリー機能を付けて欲しかったなぁと思うわけです。
と言うのもネットで検索した所、コーヒーの抽出温度は80℃台が良いという意見が増えているからです。
(当然流行りもある気がします)
一方、紅茶ならば、もっと高い温度だし、緑茶や煎茶は逆にずっと低くなる。
飲み物は、趣味なんですから前回使った温度が残っているのが一番良いと思うのです。
それでコストが変わるとは思えないですしね。
次回のモデルチェンジ時には、是非検討して欲しいです。
ホーム > アーカイブ > 2017年5月のアーカイブ
- 検索
- Feeds
- Meta